はあ・・・今週末も、土日両方ともワンオペで過ごす休日か・・・
しんどい・・・疲れた・・・
と、ため息をついているワンオペママさんへ。
家事に仕事に平日がっつり働いて、ヘトヘトなのではないでしょうか。
週末に夫が普通にいてくれる家庭だったら「待ちに待った週末」になるはずが…
ワンオペだと「休めない、しんどい週末」になってしまいますよね。
ワンオペワーママ歴5年の私が、2年以上の数えきれないほどの失敗を経てたどり着いた「ワンオペ休日をストレスなく過ごすためのポイント3つ」をまとめてみました。
ワンオペ休日に悩むママさん方の参考になれば嬉しいです。
そもそも、ワンオペの休日が疲れるのはなぜ?
「ワンオペの休日が疲れる理由」は、大きく分けて2つあると考えています。
予定が思い通りにいかない。
まずはこれ。子どもと過ごす時間は思い通りにいかないことばかりです。
前もって予定を立てていても、子どもの気分とか機嫌とか体調によって変えざるを得ないことが多いです。
あと天気にも左右されます。晴れなら外出しやすいけど、雨の日のワンオペは基本的にげんなりです。
子どもとの時間は楽しく感じることもありますが、ワンオペだとしんどく感じてしまうというのが現実ではないでしょうか。
とにかく体力が削られる
2番目の理由はこれ。
単純に、ワンオペだと全てを自分ひとりでやらないといけないので疲れる。
ひとりで子どもを見ている分、おかあさん方のHPが減りやすいです。
なので「パパが家にいるときよりも疲れやすい」と思って行動することが大事です。
ここまでを踏まえて、私が取り入れているポイントを3つご紹介します。
ポイント①子どもと話し合って予定を立てる

これはワンオペ休日が疲れる理由その1、思い通りにいかないことへの対処方法です。
まずはじめに、
休日の過ごし方の予定、どんなふうに決めていますか?
一日の予定をお子さんとシェアしていますか?
もし親だけで休日の過ごし方を決めて、子どもにはその場その場で「次はこれだよ」と子どもに伝えている場合。
そして、子どもが「そんなの嫌だ」とぐずってしまってうまくいかないことが多い場合。
あらかじめ「一日の過ごし方」を伝えるだけで、休日の子どものぐずりやストレスが劇的に改善する可能性があります。
さらにスムーズな一日にしたかったら、親子で「今日は何したい?」と話し合って決めるのがおすすめです。
親が一方的に予定を決めて伝える方式にしないことが大切です。
私自身、子どもが外出先でごねたり、思うようにいかなくてすごく疲れたという失敗パターンを振り返って気づいたのは、
「私がこう過ごしたい」という一日を子どもに押し付けていたことでした。
その逆に、子ども自身がその日の予定に納得していると、子どもは基本的にご機嫌で過ごすことが多く、イヤイヤすることがほとんどなかったのです。
このことに気がついてからは、「お互いの希望を話し合って、すりあわせてから出かける」というスタイルをとっています。
話をする時間はかかりますが、これにより外出のストレスが軽減されました。
大人が複数いる場合は、一日中子どもの好きなようにさせることもできるかもしれません。
でもワンオペの場合はそうはいきません。
子どもの要求を満たしつつ、自分のやりたいこともやって、家事なども並行してやらないといけないのです。
そのためには子どもに事前に説明しておく必要があります。
どう説明するかというと、
子どもにやりたいことがあるように、大人にもやりたいことがある
子どものやりたいようにだけして一日を過ごすことはできない
協力してお互いのやりたいことを両方できるように段取りを組むことが大切だ
ということです。
これ、大人にとっては当たり前すぎる事実だけど、
子どもにとっては知ったこっちゃないです。
言ってもすぐには理解しきれないこともあるかもしれません。
それでも何度でも伝えながら、相談しながら一日のスケジュールを組んでいくことが、ワンオペ休日をラクにするためのポイントかなあと思っています。
すり合わせのしかた
ステップ①まず子どもに「今日何したい?」と聞く
子どもに何したい?と聞くと、
電車に乗りたい!
公園に行きたい!
本屋さんに行きたい!
などなど、色々子どもからの要望が出てくると思います。
それらを全部聞いたら、とりあえず「(できるかどうかはおいておいて)気持ちはわかった」と伝えます。
いったん受け止めるのがポイントです。
やりたいことが多すぎてイラっとしたとしても「そんなにいっぱいできるわけないでしょ!」とか言わないほうがいいです。
とりあえず「気持ちはわかった」というだけで十分です。
ステップ② 自分(親)の希望を伝える
次に自分の気持ちを伝えます。
「次はお母さんのやりたいことを言うね。
お母さんは家の掃除をしたい。あと、買い物をしたいからスーパーに行きたい」
という感じで伝えます。
※このとき多くても2個くらいまでにとどめた方が平和です。
ワンオペのときは多くを望まないほうがよいです。
自分のため、にです。厳密には、自分のメンタルをイライラせずに保つために、です。
理想的なタイムスケジュール
子どもがまだ昼寝が必要なくらいの小さい年齢の場合。
個人的な理想の行動パターンは、
午前中に外出をして、13時くらいまでに帰宅してお昼寝
です。
できるだけそのタイムスケジュールにのった感じで予定を決めていきます。
眠くてぐずる可能性をできるだけなくしたいからです(ぐずられるとイライラするから)
たいがいの場合は、時間内に子どものやりたいことを全てかなえるのは難しいと思います。
なので選択肢を出して決めていきます。
子どもに、
時間が足りないから、子どものやりたいことすべてはできないこと
だから、どれかを選ばなければいけないこと
を伝えます。
「時間が足りないから、今日は電車に乗るか公園のどちらかしかいけないけど、どっちがいい?」と聞いて、子どもに自分で決めてもらいます。
大事なのは、子ども自身に決めさせることです。
子どもが自分で決めて、納得することが大事だからです。(あとでぐずりにくくするために)〇
子どもが迷っている場合は、それぞれの選択肢のメリットとデメリットを伝えたりして助け舟を出すこともあります。
たとえば、
「電車に乗りたいなら今日乗ったほうがいいかな。
明日は予定があるから、電車には乗れないから、今日乗らないなら次に電車に乗れるのは来週になると思う。
公園は明日でも行けるよ」とか。
自分で決めさせることの何が良いかというと、後で「自分で決めたんだよね」と言えることです。
子どもがぐずったときに、「自分で決めたことなんだから守ろうね」と言いやすいのです。
親が勝手に決めたことと、子どもが自分で決めたことのどちらが納得感を持ちやすいか。
私は圧倒的に後者かなと思うので、時間がかかっても、どんなに小さなことでも、子どもに決めさせることを重視しています。
その日のスケジュールを子どもに話す
それぞれの希望を出し合い、すり合わせまで終わったら、子どもの予定と大人の予定を組み合わせて、一日のスケジュールを最初から最後まで子どもに話していきます。
「じゃあ今日は、
まず家の掃除をしてからおでかけの準備をして、
そのあと電車に乗っておでかけして、
帰りにスーパーに寄って帰ってこよう。
お昼ご飯は家で作って食べよう。
お昼ご飯を食べ終わったらお昼寝しよう」
という感じで一日の流れをバーッと話していきます。
この一日の流れがあるだけで、子どもは気持ちの準備ができるようです。
「次は何だっけ」「お昼寝だね」という感じで一日がスムーズに流れていくようになりました。
「まだ眠くない、お昼寝したくない」とごねることも圧倒的に減りました。もちろん時々はありますが。
大人だって次の予定が見えない中ではなんとなく生活しにくいものだと思います。
目の前のことを目いっぱい楽しみたい子どもならなおさらだと思うのです。
そんなわけで、我が家はこの事前に一日の流れを「話し合って」決めるステップのおかげで、ワンオペ休日でもイライラが少なくできています。
もちろん子どもの性格や親自身の性格によって、このやり方が合う合わないはあると思います。
あくまで一例ですが、我が家の場合はこのやり方がベストでした。
ちなみに我が家では子どもが2歳になる前くらいから、5歳になる今までずっとこのやり方でやっています。
我が家は子どもがひとりなので、子どもが複数いる家庭はまた事情が違うかもしれません。
でも基本的に大切にするべきことは「子どもと話し合って決めること」。
このポイント自体は、子どもの人数に関係なく、大切なんじゃないかなと思っています。
ポイント②万全の準備をして出かける

ここではワンオペ休日が疲れる理由その2「体力が削られる」への対処法を書いていきます。
ワンオペ休日でおでかけをする場合は、ありとあらゆる準備をバッチリしていくのをおすすめします。
便利な世の中なので、正直お金を払えばたいていのことはなんとかなります。
雨が降ったら傘を買えばいいし、水がなくなっても買えばいいし、お腹が空いたら食べ物を買えば良いです。
でも大人だけならなんでもない小さなことでも、子どもがいるといちいち手間取ります。
傘を買うためにコンビニを探す
水を買うために自販機を探す
パンを買うためにパン屋さんを探す
など、そのひとつひとつをこなすためにエネルギーを使って疲れてしまい、結果イライラしてきます。
疲れてしまうと子どもにキツく当たってしまったりする負のスパイラルが生まれます。
一度疲れてしまうとなかなか回復が難しいので、特に外出先では「◯◯しなきゃいけない」という状況になることを極力減らすほうがいいです。
どんなに小さいことでも手間をなくしましょう。
自分のHPを温存しましょう。
そのために準備を徹底します。
ちなみに、私が外出時にカバンの中に入れているものは以下です。
近場のおでかけの場合
・お手拭き(ある程度の量)
・着替え一式
電車に乗るくらいのお出かけの場合
・お手拭き(ある程度の量)
・着替え一式
・水筒(大人用、子ども用)
・子ども用の予備の水(未開封の小さめペットボトル)
・傘、カッパ
・お菓子やパン(小腹が空いたときにさっとあげられるもの)
・ミニ絵本やトミカなど小さなおもちゃ(何かに飽きたときに、さっと注意を引いて時間をかせげるもの。おすすめ絵本は下の方で紹介してます)
・羽織もの(寒いときに羽織れるもの)
・フェイスタオル(何か濡れたり汚れたりしたとき用に)
一日レベルで出かける場合
・お手拭き(ある程度の量)
・着替え一式
・水筒(大人用、子ども用)
・子ども用の予備の水(未開封の小さめペットボトル)
・傘、カッパ
・お菓子やパン(小腹が空いたときにさっとあげられるもの)
・ミニ絵本やトミカなど小さなおもちゃ(何かに飽きたときに、さっと注意を引いて時間をかせげるもの。おすすめ絵本は下の方で紹介してます)
・羽織もの(寒いときに羽織れるもの)
・フェイスタオル(何か濡れたり汚れたりしたとき用に)
・シールセットなど30分くらい注意を引けるもの
・お気に入りのタオルや人形などの落ち着くもの
を持っていきます。
そんなわけで私は常に大荷物なのですが、おかげでイライラは少ないです。
これらの持ち物はすべて、自分の心の安定のために必要なものと割り切って持ち歩いています。
ポイント③子どもと一緒に昼寝して、子どもといるときに自分時間をもつ

ここでもワンオペ休日が疲れる理由その2「体力が削られる」ことへの対処法を書いていきます。
基本的にワンオペ休日の場合は、子どもの昼寝に合わせて私もガッツリ寝ます。
昼寝はだいたい1~2時間くらいです。
昔は昼間に寝すぎると夜が寝られないタイプだったのですが、今は昼寝しても夜は自然に寝れます。それくらい育児は疲れるものです。
睡眠不足はイライラに直結するので、前日もできるだけ夜ふかししないようにしています。
できるだけ睡眠を取るようにし、体調も常に万全でいられるように気を配っています。
でも。ワンオペだから、もともと自分ひとりの時間が少ないうえに、昼寝まで子どもと一緒にしてしまったら…
完全に自分の時間がなくなってしまいますよね。
このへんの葛藤は何度もあり、色々試してみました。
自分の時間を確保するために夜更かししてみたり、
子どもが昼寝する時間に起きたり。
でも
自分の時間をもつために無理するよりは、自分の時間を諦めてしっかり休んだ方が良い
というのが、この5年に及ぶワンオペ生活で出した結論です。
その代わりに「子ども起きている時間にも自分のやりたいことをやる」ことでバランスを取ります。
「お母さんは今からこの雑誌を読みたいので、◯◯分までそれぞれ自由時間にしよう」という感じで、子どもが起きているときに自分のやりたいことをやります。
まあ、宣言しても子どもがイヤイヤモード、構ってモードになってしまうとそういうわけにもいかないのですが。。。
でも、子どもはふとしたときに、ひとり遊びを始めることがあります。
そんな瞬間が生まれたら、ぜひ自分時間を持ってください。お気に入りの雑誌でも手に取って、コーヒータイムでも楽しんでください。
せっかく生まれた自由時間のチャンスに、たまっていた家事を片付け始めたらダメです。
ワンオペの民には癒しの時間が必要なのです。
ぜひ子どもと一緒にいるときにも自分時間を作って楽しむ、を意識してみてください。
ちなみに子どもが5歳になった我が家は「休日にそれぞれがしたいことをする時間」というのが生まれています。
子どもは子どもの読みたい本を読み、私も私の読みたい本を読む、という時間を持てるようになりました。
5歳は少しずつ文字が読めるようになってくるので、自分ひとりで絵本を読み始めるんですね。
子どもに手がかかる時期って、永遠のように思えるけど、実はそこまで長くないです。
体感的には子どもが3歳になるとぐっと楽になります。
「ついに、ここまできたか・・・」と、じーんと感動する日も、すぐそこまでやってきています。
その日を楽しみに、今日も乗り越えましょう。
余談

自分の時間がなさすぎて心身が疲れてしまったら、有給を取ってリフレッシュするのもいいと思います。
本当は土日で休むのが本来あるべき姿なのでしょうが、ワンオペワーママ生活を送りながら土日に休むのは難しいです。(少なくとも、私は難しかったです)
なので、1~2ヶ月に1回ほど、有給を取って休んでいました。
正直な話、この有給を取っていたから自分のメンタルが崩壊するのをなんとか防げていたという感じです。
子どもが小さければ小さいほど、いつ熱を出すかわからない怖さもあるし、有給を取るのをためらったりする気持ちもあるでしょう。
私の会社は福利厚生がないようなもので、有給も10日くらいしかありません。
だから有給を取るのにかなりの勇気が要ります。でも有給がなくなったらそのとき考えればいいかなと諦めています。
先を見越して有給を残しておくよりも、「今」の自分を休めてあげることが、長く働き続けるには大事なことだと思っています。
なので、疲れ果てているワーママさんには、ぜひ無理やりにでも有給を取ってみてほしいです。
効果的なリフレッシュになると思いますよ。
そうはいっても仕事が忙しくて休めないんだよ!という人もいると思います。
そんな人は、
・ランチに美味しいお店でご飯を食べる
・読んでいると落ち着いてくる本を読む
・子どもが寝静まってからひとりでこっそりハーゲンダッツを食べる
とかして、少しずつストレスを解消していく方法を見つけていくのがよいかもしれません。〇
以上、我が家なりの母子休日を楽しむためのポイントでした。
これはあくまでひとつの例ですが、ワンオペ生活に悩む方の参考になれば嬉しいです。
我が家で使ってよかったもの紹介
持ち歩いていた絵本たち
子ども1~2歳
うびだす!うごく!の「てのひらえほん」シリーズは4冊も持っていました。1冊で10~15分くらいは間が持つので、1~2歳の間は重宝していました。
とびだす!うごく!たべもの(てのひらえほん)| Amazon
とびだす!うごく!どうぶつ(てのひらえほん)| Amazon
子ども2~3歳
少しずつ電車の移動も慣れてきたころ。景色を見て楽しんでくれることも増えましたが、飽きてきたときのために小さな絵本を持ち歩いていました。
はらぺこあおむしのミニサイズの絵本をいつもカバンの中に入れていました。
バーバパパのミニ絵本も好きです
3歳のときに買って、5歳半になる今でも繰り返し読んでいるのがこの『新幹線のたび』という絵本。
おでかけ版 新幹線のたび with English (講談社 MOOK) | Amazon
青森から鹿児島まで新幹線で行くというだけの絵本なんですが、新幹線の名前だけでなく駅名や山の名前なども書いてあって、地図帳としても良いかなと思って買いました。
日本語だけでなく英語も書いてあるので、ちょっとした英語に触れる機会にもなります。
子ども4歳
おしゃべりで時間がもつようになり、絵本はなくても時間をつぶせるようになってくるころ。
それでも長時間の移動では飽きてきてしまうので、色鉛筆とノートをリュックの中に入れていました。
最近ではトンボのミニ色鉛筆が小さくてちょうどよいので、おでかけのときには持ち歩いています。
旅行や新幹線での長時間移動のときには、新幹線のスタンプセットも持参。これで20~30分くらいは持ちます。(3歳のときに与えたけど、使い方を理解して楽しんで遊ぶようになったのは4歳後半以降でした)
以上、ワンオペワーママ生活をストレスなく過ごすための方法まとめでした。
ワンオペ関連の記事はこちらから
いくつか厳選してみました↓
ワンオペワーママの体調管理【倒れないで働きつづけるには?】メンタル編&仕事編
ワンオペワーママの体調管理【倒れないで働き続けるには?】家事編
。
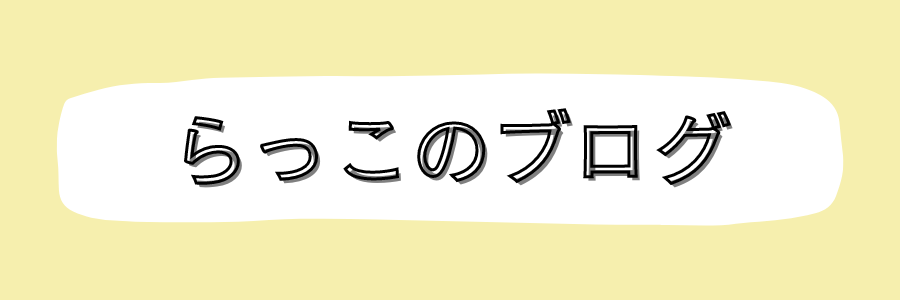



コメント